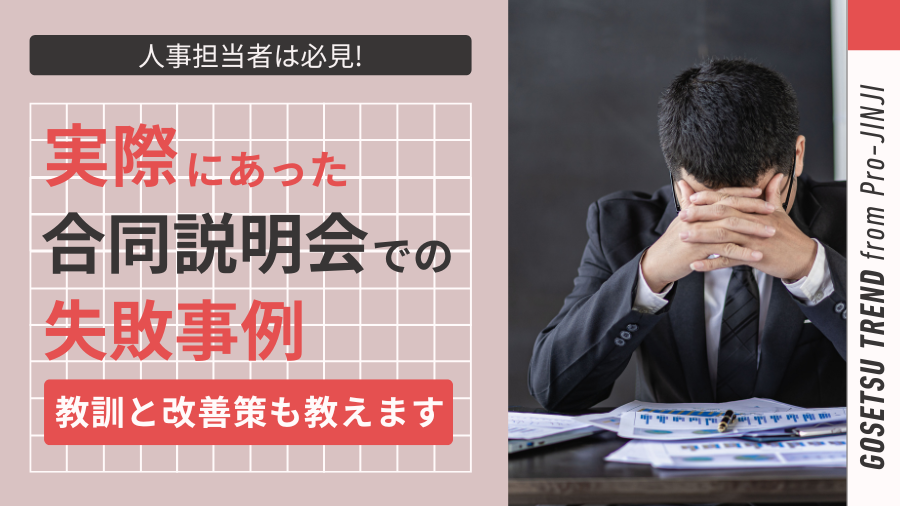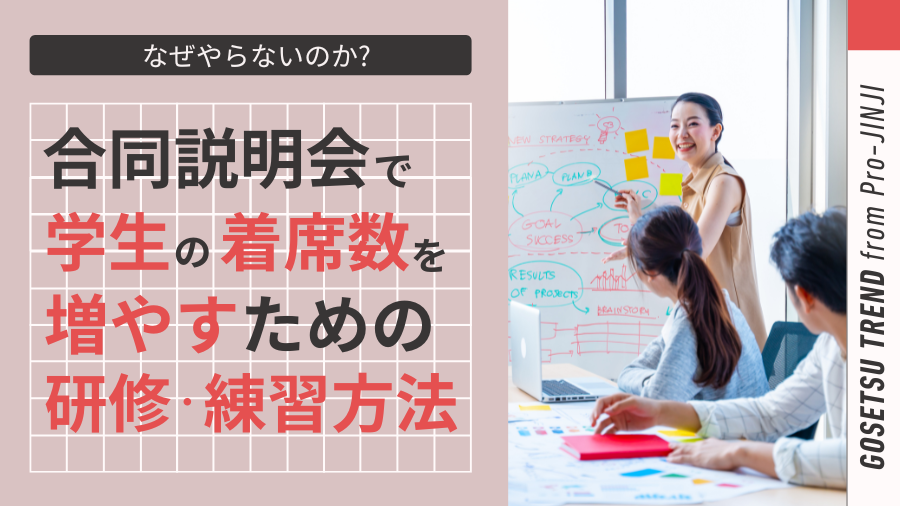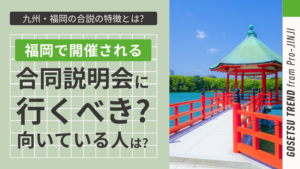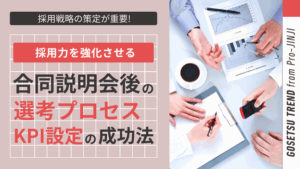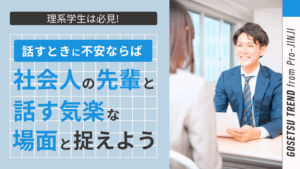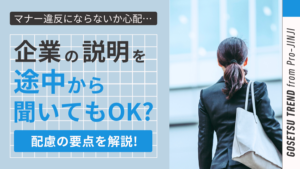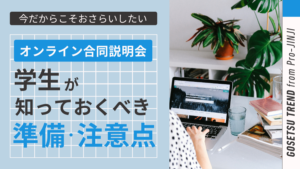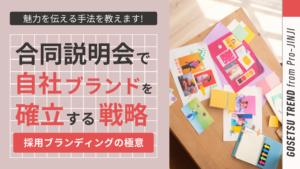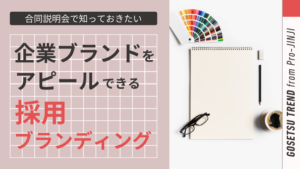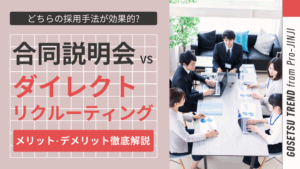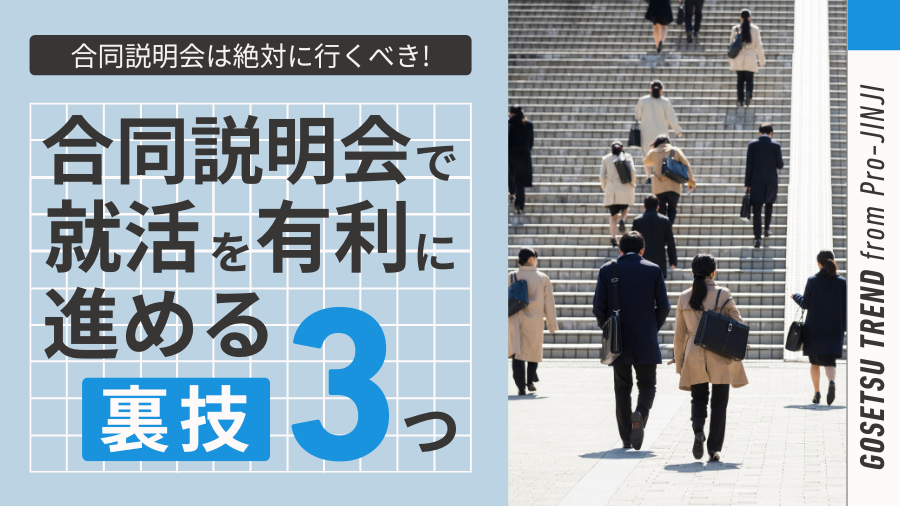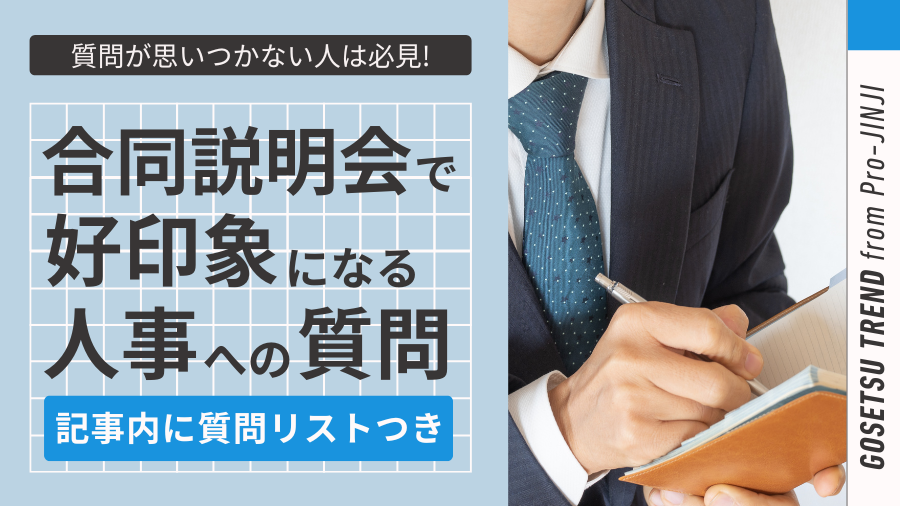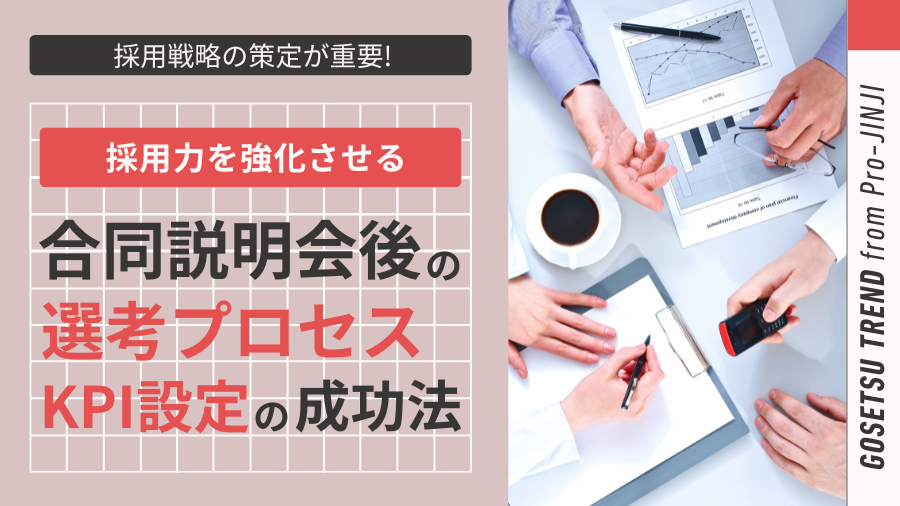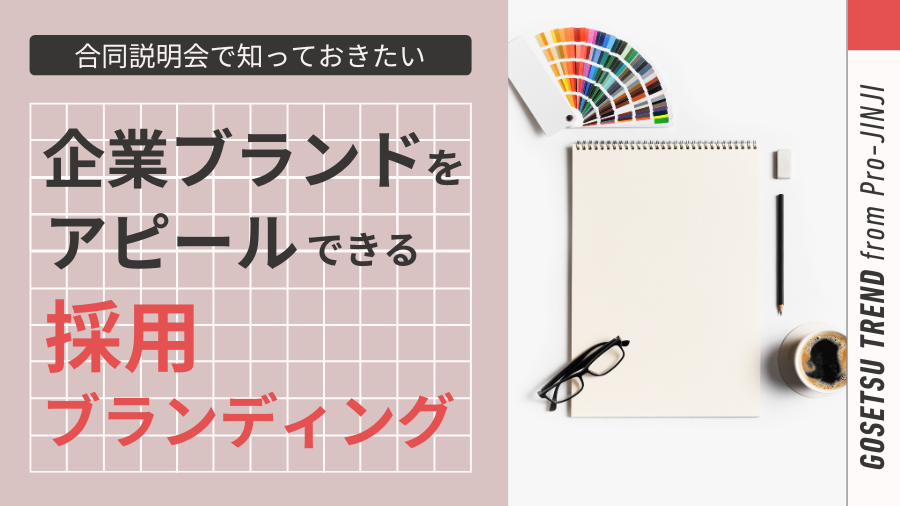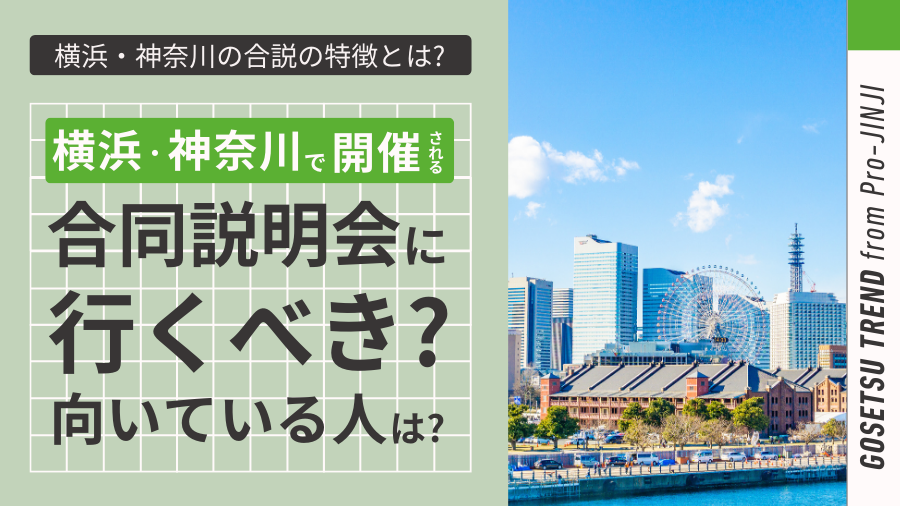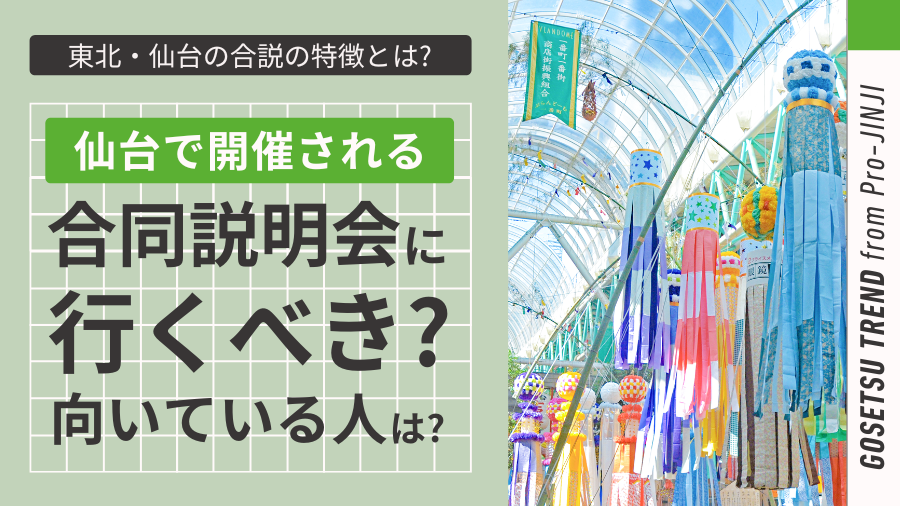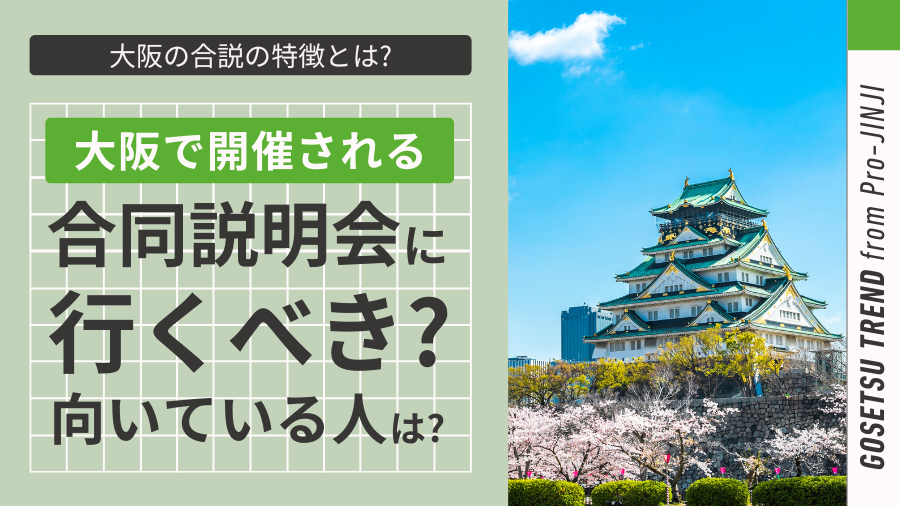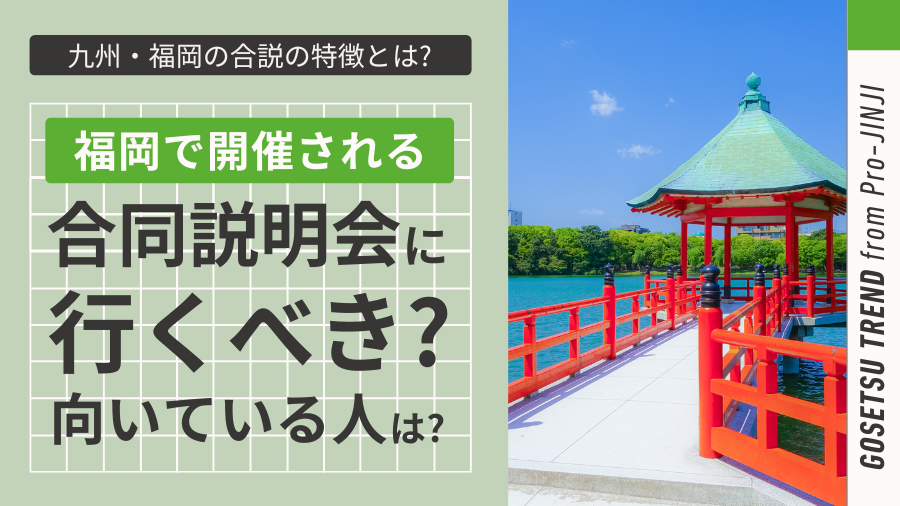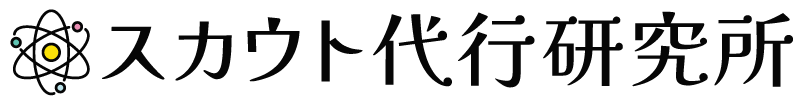こんにちは。プロ人事です。
今回は企業側の視点で、合同説明会で起こりがちな失敗と、そこから得た教訓をご紹介していきます。
特にぜひご確認頂きたいのは、人事の方が一見「それは大した失敗ではないのではないか?」ということが、実は学生の集客においてクリティカルなダメージがあるケースになりえるということです。
逆に人事の方が「血相を変えてしまうほどの大失敗」が、実はそこまで大きなマイナスの影響がでないこともあります。
具体的にどのような事例か、早速ご紹介しましょう。

合同説明会の運用にお困りですか?
株式会社プロ人事では、合同説明会の運用代行やご相談に応じています。
プロの人事が展開する採用サポートをご体感ください。
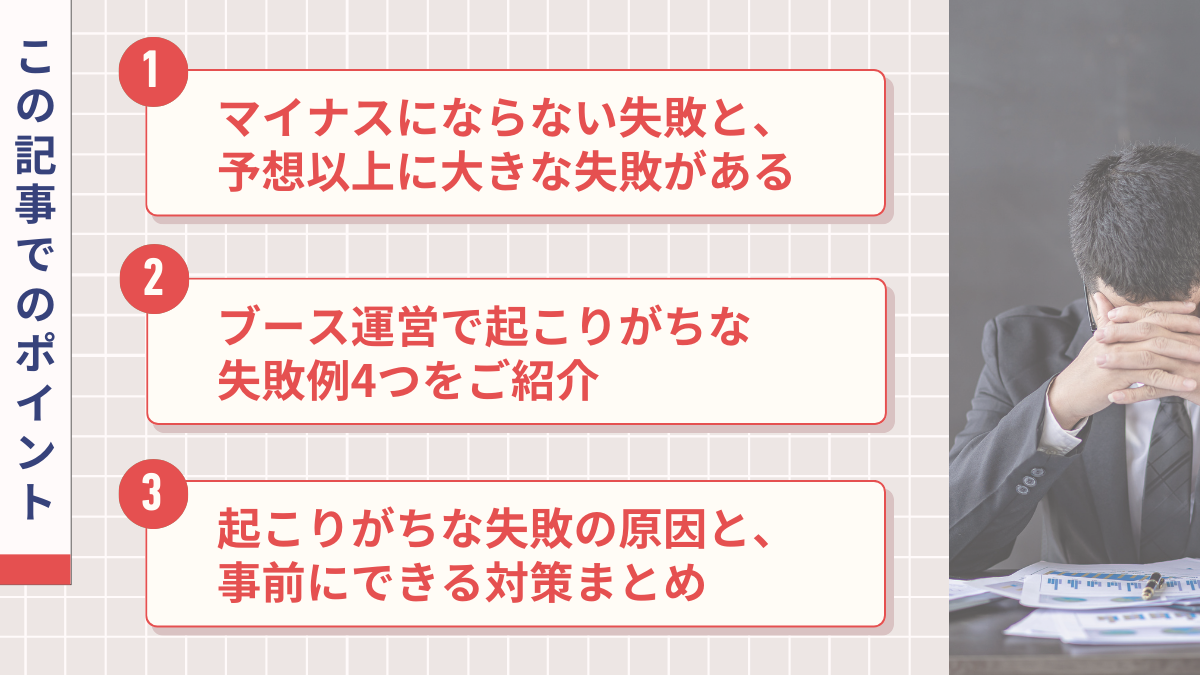
失敗事例①:チラシが少なすぎてなくなってしまった
合同説明会のご支援を多くやってきた際に、頻出のトラブルです。
しかも、学生の集客においてかなりマイナスの影響が出てしまう失敗事例です。
チラシの用意がない=そこまで採用に力を入れていないと就活生に捉えられてしまうリスクが高いからです。
また、チラシがなくなるほど人気すぎると誤解され、同業他社に就活生が流れてしまう可能性もあります。
人事の方々の多くは「笑って済ませる」ようなケースも多いようですが、学生を集めるという意味においては大ダメージです。
このような事例にて、近くのコンビニに走って白黒のコピーを取ってくるようなケースが多いです。
しかし、白黒のコピーでは就活生に与える印象は良いものとは到底言えません。
コンビニまでの往復やコピーの作業に大きく時間が取られてしまうのも、非常にもったいないです。
想定される原因
では、なぜチラシが足りなくなってしまうのか。いくつかの原因を見ていきましょう。
- 原因 ①:参加者を最初から少なく見積もってしまった
-
根本的に、「そこまでブースに多くの就活生が来ないだろう」と最初から少なく見積もってしまったケースです。
当日ブースに参加する就活生が少ないのではないかと思う気持ちはわかります。
しかし、そこで参加者を少なく見積り、チラシを用意しないのは非常にもったいないです。 - 原因 ②:人事が手持ちでチラシを持ってくる
-
大きい会場ではよくあることですが、搬入で人事が手持ちでチラシを持ってくることはあまりおすすめしません。
確かに、搬入・搬出で車やトラックを使うことは、配送料や駐車場の利用料金などのコストはかかります。
とはいえ、人が1人で持ち込める量は限りがあります。持ち込みで体力を大幅に使ってしまい、ブース運営に影響が出てしまうかもしれません。
- 原因 ③:「チラシが足りなくなる」シチュエーションを想定していない
-
参加者を多く見積もってチラシを発注し、当日用意したとしても思わぬところでチラシが足りなくなる場合があります。
このような事例が起こりがちです…!
- 予備のチラシが他の備品と混じってしまった
- 郵送や発送の手違いで予備分のチラシが会場に届かなかった
- 原因 ④:チラシが足りない時の影響を過小評価している
-
先ほどお話した通り、「チラシが足りなくなったとて影響は少ない」と考えている企業は一定数います。
しかし、チラシの不足は就活生が企業に興味を持ってもらうチャンスを逃してしまうことと同じです。
企業でできる改善策
では、チラシがなくならないように企業で対策できることはあるのでしょうか。
以下にプロ人事がおすすめする改善策をお伝えします!
- 改善策 ①:最低限の枚数を確保する
-
当日は自分たちの予想に反して参加者が多くなることはよくあります。
チラシを発注する際は気持ち多めに参加者の数を見積りましょう。具体的なチラシの枚数や発注方法については、事前に社内で話し合い、マニュアルを作っておくと後の対応がスムーズです。
- 改善策 ②:タペストリー内に予備のチラシを忍ばせる
-
どんなに多めにチラシを用意していても、思わぬ形でチラシが足りなくなりケースがあります。
それを予防するためにも、複数の場所にチラシを保管し、一箇所で不足しても他の場所から確保できるように準備しておきましょう。用意するチラシは、単独説明会の日程が記載されていない汎用的なもので差し支えありません。
- 改善策 ③:チラシは郵送または車で持ち込む
-
多少コストはかかりますが、チラシをはじめとした機材は車で持ち込むか、郵送で会場まで発送してもらうことをおすすめします。
営業車で持ち込む場合は、渋滞で遅れないように事前に近くの駐車場を調べ、時間に余裕を持って持ち込みましょう。
郵送で送る際は他の備品とまぎれないよう、伝票にブースに直接運んでもらうよう記載します。
会場ごとに搬入の指定がある場合は、そのルールに従いましょう!
失敗事例②:ブースのタペストリー・ポスターがない
こちらはまれに発生するトラブルです。
ブースの見た目が少しさみしくなりますが、実は学生の集客においてそこまでマイナスの影響はありません。
もちろん、ブースに座ってくれた学生のユーザー体験の質に関わるのであるに越したことはないですが、学生の集客だけを見るとそこまで影響がありません。
それよりも、人事がトラブルに対して過剰反応してしまうことに対する悪影響のほうが大きいでしょう。
目に見えてブースがさみしくなるため、人事側が激昂したり、社内に何度も問い合わせて無理やり機材を送り届かせようなどとしたりして、当日の運用を放棄してしまうケースがあるからです。
あるいは、「機材がないから今日は無理だ」ということで諦めてしまうような人も結構います。
とはいえ、この失敗に関しては十分に「ピンチをチャンスに変える」ことができる事例です。
次の原因と対策を読んでブースの運用に前向きに取り組んでいきましょう!
想定される原因
- 原因 ①:郵送の手配が上手くできていなかった
-
合同説明会に慣れていない企業で起こりがちなケースです。
過去にプロ人事が担当した企業では、次の理由で配送トラブルが起こっていました
- 送ったはずだが何らかの事情で届かなかった
- そもそも、配送手続きを忘れて送っていなかった
- 直前に送ったので、当日までに配送が間に合わなかった
- 配送後、会場の別の場所に保管されていた
- 本来送るべき場所ではないため、受取拒否され戻ってきていた
- 原因 ②:同日に複数の合説があり、どうしてもタペストリーが足りなかった
-
これは合同説明会に慣れている企業の場合に起こりがちなケースです。
タペストリーは用意のコストがかかり、保管場所も多くの場所を取ります。
これはやむを得ないケースだといえるでしょう。 - 原因 ③:根本的に、ブースの機材が少ない
-
合同説明会に出展するのが初めて、または回数が少ないと使える機材が限られてしまいます。
そのため、用意するのに時間がかかったり、手配が間に合わなかったというケースが見られました。
企業でできる改善策
- 改善策 ①:事前に郵送の手配を確認する
-
会場宛に発送された際に、どこに保管されるか、届いたことをチェックできるか確認できるようにしましょう。
合同説明会の規模や使用する会場によっては、発送方法が指定されているケースがあります。
そちらも事前に確認した上で、受け取りや搬入方法は会場のルールに従いましょう。
失敗事例③:プレゼン力がたどり着いていない
合説においてプレゼンする力があまりにも低い場合、散々な結果になってしまうケースがあります。
ある程度、資料を読んで、棒読みであっても最低限の成果はでるはずですが、「声が小さすぎる」「あまりにも自信がない様子」といった理由にて、学生が興味をなくしてしまうのは非常にもったいないです。
企業でできる改善策
- 改善策 ①:研修と練習を重ねよう
-
プレゼンに必要な話術や立ち居振る舞いは練習で向上させることが可能です。
研修を開く際は、複数名でプレゼンをロールプレイングを行い、フィードバックを提供しあうことが有効でしょう。
合同説明会の運用代行、研修はプロ人事へ!
プロ人事では合同説明会を活用する支援を行っています。
サービスの導入、ご相談はメールフォームからご相談ください!
2営業日以内に担当者よりご連絡させて頂きます。\ 期間限定・今なら無料の初回コンサルティング付き!/
無料の初回コンサルティングは予告なく終了する場合がございます。
- 改善策 ②:スライドのクオリティを向上しよう
-
プレゼンで話術が長けていても、スライドのクオリティが低いと魅力が伝わりにくくなります。
あわせてスライドのデザインも確認し、しっかりと作り上げましょう。
合同説明会のプレゼンと研修はこちらの記事で詳しく解説しています!

失敗事例④ : 人材不足で対応力が不足している
ブースを1人で運用する場合も要注意です。
確かに、合同説明会のブースを1人で行っている企業もあります。
この場合は超人気企業だったり、マイナビ・学情以外のマイナー企業主催の合同説明会であれば1人でも運用することが可能です。
しかし、マイナビEXPOに出展する場合はあまり人気ではない業界の企業での最初から失敗前提と言えるでしょう。
なぜ1人でのブース運営はおすすめできないのか?
その理由は、1人だと同時に複数の対応ができないからです。
合同説明会ではブースの呼び込みが集客の向上につながります。
しかし、もしブースの運営を1人で行い、プレゼン中だったらどうなるでしょうか。
「1人がプレゼン中の場合は、ブースへの呼び込みができない」ことになります。
もちろん、学生側がどうしても座りたい、話を聞きたいと思えるような企業であれば1人でも運用できる場合はあるでしょう。
プレゼン開始日時と、説明終了後に個人情報のQRコードを読み取るために順番に来るよう説明書を置いておけば、人気企業であれば学生もスムーズに対応できます。
とはいえ、人気企業で1人しか来ないケースは比較的まれです。
逆に、学生から知名度の低い企業なのに1人しかブースにいないケースは非常に多いです。
学生を呼び込むことすらせずに、椅子にぼんやりと座り続け、学生が話を聞きたいですと声をかけてくれて初めて説明しだすような人事は、実は合同説明会においてかなり多いです。
この場合は朝から夕方まで合同説明会をやったところで、10名以下の集客になる傾向がありました。
企業でできる改善策
- 改善策 ①:複数名でブースを運営する
-
合同説明会では複数名でブースを運営することが必須です。
人数はプレゼン担当と呼び込み担当の、最低でも2名は確保する必要があるでしょう。それぞれの役割に徹することで、より多くの就活生をブースに呼び込める確率が高くなります。
人数を複数名確保できれば、ブースでの搬入・搬出もスムーズに動けるのは大きな利点ではないでしょうか。
また、ブース内の備品の確認もより時間を短く終わらせることも可能です。業務が忙しい時に人数を確保することは大変だとは思います。
しかし、合同説明会の運営を成功させるためには、複数名での対応が欠かせません。
できる限り社内全体で協力して、ブース運営をしていくことをおすすめします。
備えあれば憂いなし。事前に対策しよう
一見、突発的なトラブルが起こった場合を想定すると心配になる気持ちはあるのではないでしょうか。
しかし、合同説明会の失敗は準備で防げるものと、運営上影響がないものがあります。
事前に起こりがちな失敗事例を把握した上で、対策をしておくことに越したことはありません。
余裕を持ったブース運営を行えば、企業の魅力をより強く就活生にアピールできます。
備えあれば憂いなしです。
合同説明会の限られた時間で、最大限学生の心に響くブース運営ができるよう、事前に対策していきましょう。
“合同説明会トレンド” では、この他にも合同説明会の参加に役立つ情報を発信しています。
ぜひ他の記事もご覧いただき、合同説明会の運用に役立てていただけると嬉しいです!