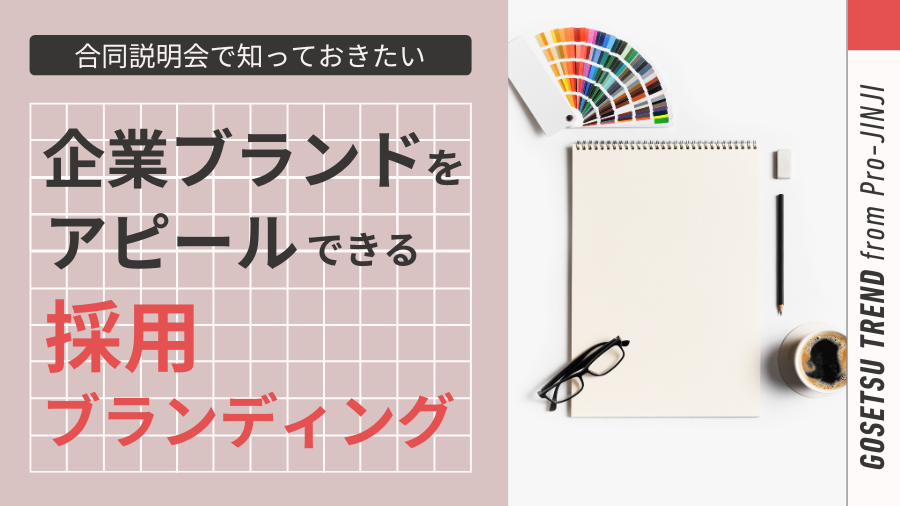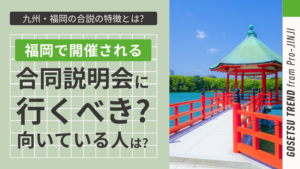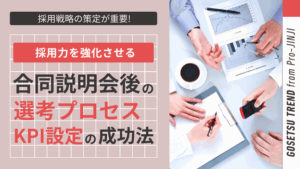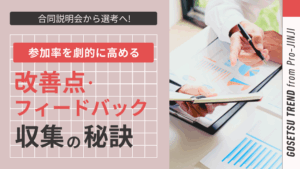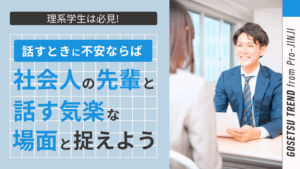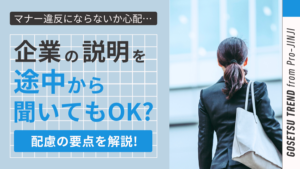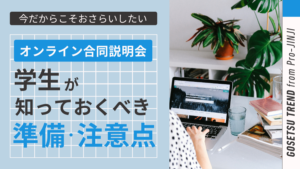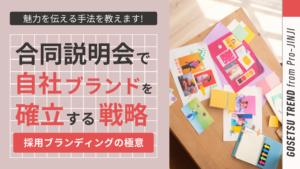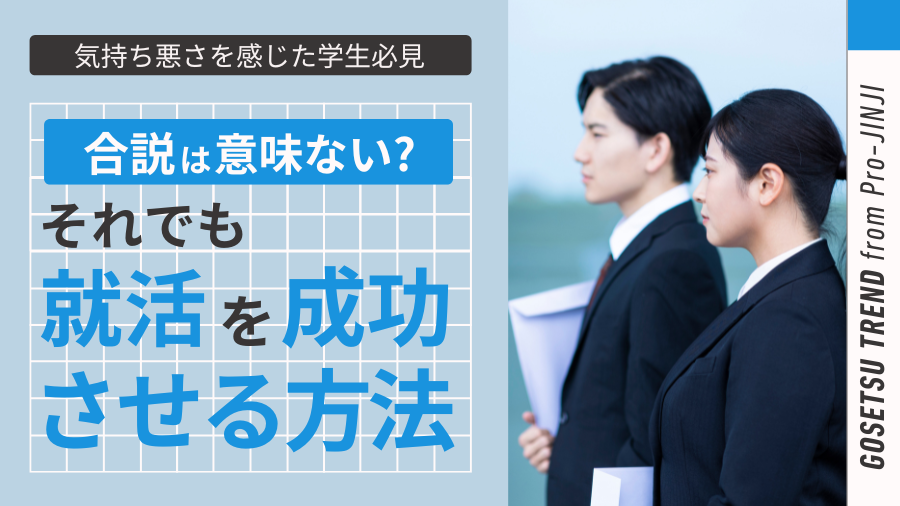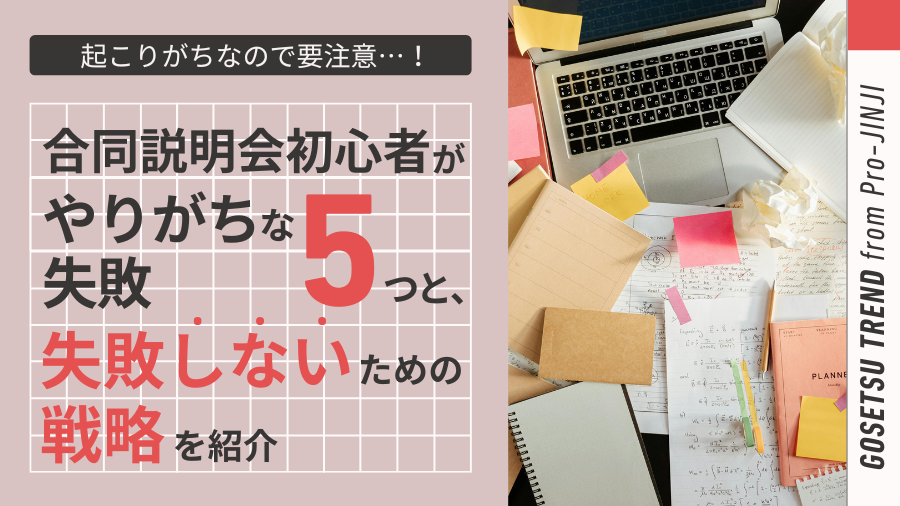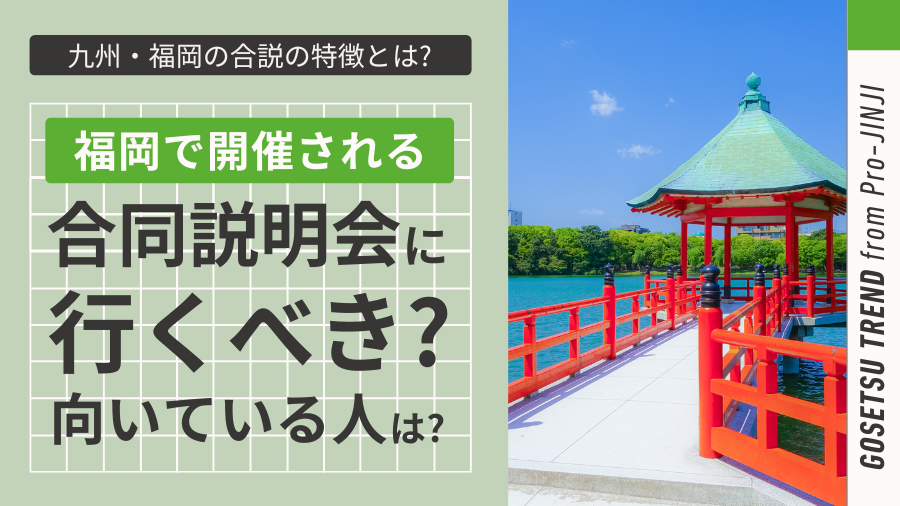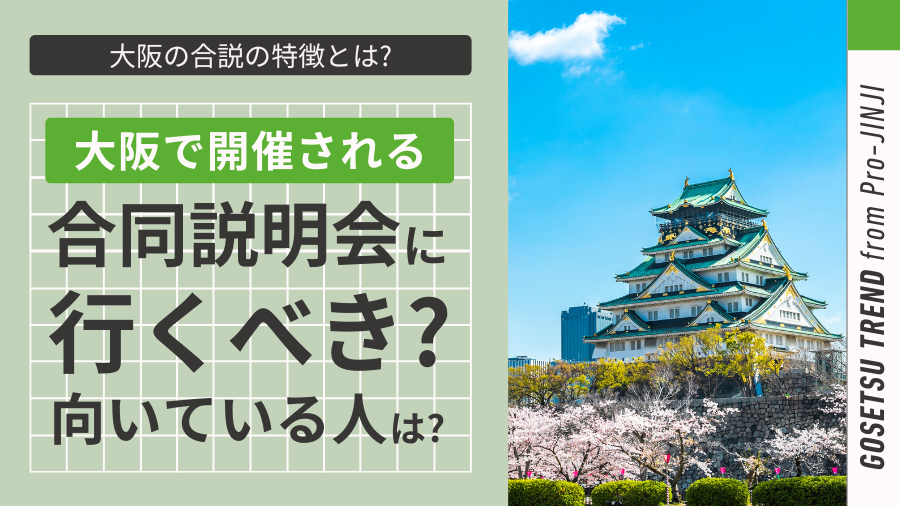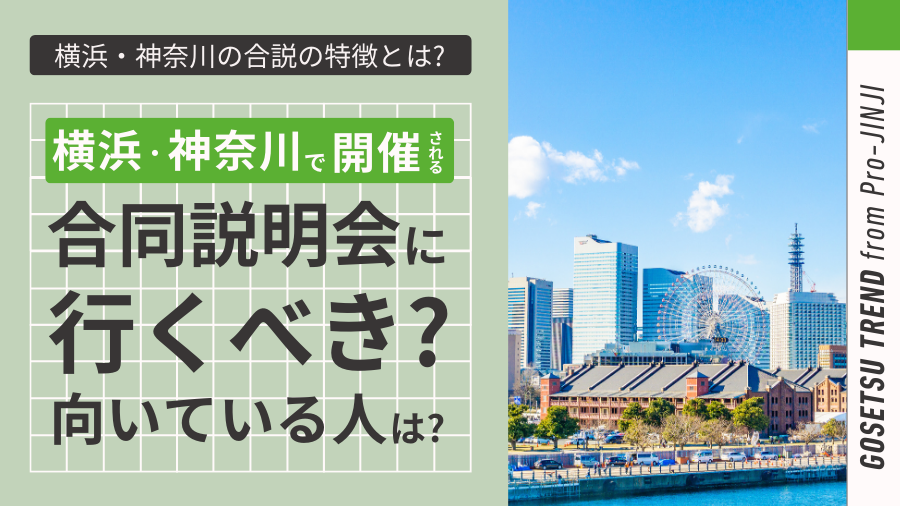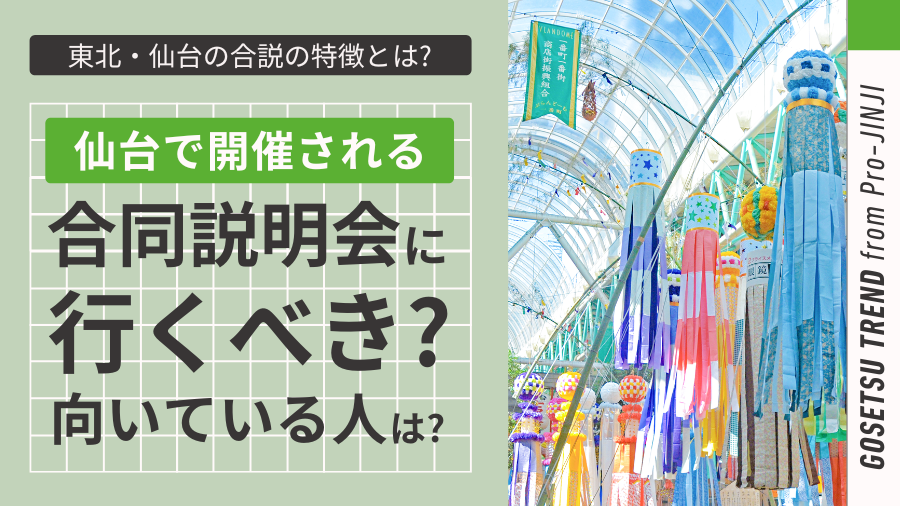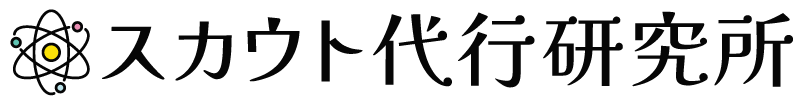こんにちは。プロ人事です。
合同説明会で学生が企業に対して魅力を持ってもらうためには、企業のブランドをアピールすることが必須です。
そのためには企業のブランドやイメージを的確に伝えるための手法「採用ブランディング」を構築していく必要があるでしょう。
この記事では、合同説明会の中でできる採用ブランディングについてご紹介します!

合同説明会の運用にお困りですか?
株式会社プロ人事では、合同説明会の運用代行やご相談に応じています。
プロの人事が展開する採用サポートをご体感ください。
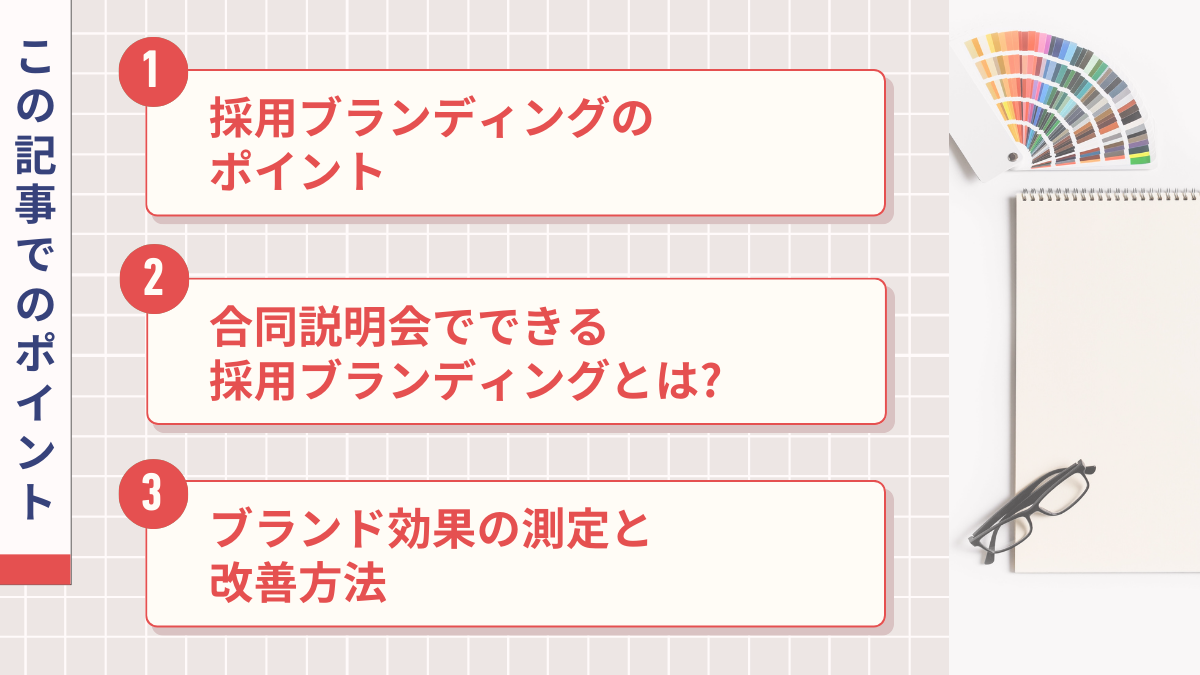
採用ブランディングのポイント
まず、採用ブランディングを行うにあたり必要なポイントを3つご紹介しましょう。
- ① 「一貫性」を保つ
-
企業のメッセージや業務の取り組みについてブレがないよう、一貫性を持たせることが重要です。
また、プレゼンのデザインやブースに使う色など、ビジュアルにも統一感を保つことも心がけましょう。 - ② 「信頼性」を持たせる
-
企業の価値観やミッションを明確に伝えられれば、学生に信頼感を与えることが可能です。
また、①の「一貫性」を保つことは、「信頼性」の担保につながります。 - ③ 「魅力的なストーリー」を作り上げる
-
学生に心に響く企業のストーリーを伝えられるよう工夫しましょう。
「なぜこの企業を立ち上げたか」「業務で何を届けたいか」を自分の言葉で真摯に伝える姿勢が、独自のストーリーを作りあげられます。
この3つのポイントを合同説明会の場所で再現させることができるかどうかが、採用ブランディングにおいて重要です。
合同説明会で行う採用ブランディング
では、実際に合同説明会でできる採用ブランディングの手法を確認しましょう。
- 出展ブースのデザイン
- プレゼンの工夫
- ノベルティの作成
出展ブースのデザイン
出展ブースのデザインは企業のイメージを伝えるだけでなく、出展ブースの目印としても活用できます。
また、ブースをきちんと装飾している企業はそれだけ採用に力を入れている優良企業であると学生が感じる手助けとなるでしょう。
特に、制作会社をはじめとしたクリエイティブ業界や、化粧品販売など女性を採用ターゲットに置く場合は、
デザイン性が重要視される傾向です。
具体的に気を配るべきポイントをご紹介します。
- ① 視覚的にインパクトのあるデザインを作る
-
ブースの「タペストリー」や「ポスター」をはじめとした機材を用意し、インパクトを与えられるブースを作りましょう。
特にタペストリーには、目を惹くようなキャッチコピーやビジュアルを配置するのがおすすめです!
キャッチコピーは企業が伝えたいメッセージを具体的に記載すると、学生の心に伝わりやすくなります。 - ② ブランドカラーやロゴを最大限活用する
-
ブースの配色はコーポレートカラーを基調にすると、全体の統一感をアピールできます。
また、「のぼり」や「椅子・テーブルカバー」にロゴを入れておくと、企業のブランドイメージをより強く伝えることが可能です。特に椅子カバーに繰り返しロゴを配置するのは「リピテーション」の手法を再現できます。
この「リピテーション」は、デザインのレイアウトにおける「構成美の要素」の1つに当てはまります。
プレゼンテーションの工夫
企業ブースのデザインと同じ観点ですが、プレゼンテーションのスライドのデザインも同じように重要です。
- ① スライドや映像を作りこむ
-
昨今ではトレンドに敏感な学生も増えてきています。
どれほどプレゼンの内容が魅力的でも、「手作り感満載の、垢抜けないスライド」だと学生の心をなかなか掴めません。
スライドは情報を的確に伝えることに加えて、デザインのトレンドや洗練さも担保できるよう工夫しましょう。 - ② プレゼンターの服装や言葉遣いに気を配る
-
学生は「プレゼンター=現場で働く社員」として見ています。
プレゼンターがハキハキと話し、服装や立ち居振る舞いが洗練されていれば彼らにポジティブな印象を与えることができるでしょう。また、当日参加する社員は服装に「コーポレートカラー」を取り入れたり、「お揃いのブルゾンやトップス」を着用するのもおすすめです!
詳細は以下の記事をご覧ください。関連記事はこちら! 【人事だって服装に悩む…!】合同説明会の理想の服装とは?【企業・人事編】 – 合同説明会トレンド 合同説明会に参加する人事にとって、おすすめの服装はどのようなものでしょうかこの記事は服装について数少ない人事・企業の参加者に向けた内容です。スーツとオフィスカジ…
【人事だって服装に悩む…!】合同説明会の理想の服装とは?【企業・人事編】 – 合同説明会トレンド 合同説明会に参加する人事にとって、おすすめの服装はどのようなものでしょうかこの記事は服装について数少ない人事・企業の参加者に向けた内容です。スーツとオフィスカジ… - ③ 動画を作るなら「徹底的に」作りこむ
-
「社員インタビュー」など、動画を配信する場合はかなり徹底した作り込みが必要です。
実際の社員は「撮られ慣れていないため」、白々しい棒読みのセリフに演技が丸出しになりがちです。
そうなると中途半端なクオリティになってしまい、伝えたいメッセージが届きにくくなってしまいます。
できる限り自然な雰囲気での撮影を心がけるとともに、場合によっては制作会社の依頼も検討するなど、「徹底的に」作り込んでクオリティをあげましょう。
「シュール」なデザインはあり?
ここ数年のトレンドとして、あえて「シュール」なデザインにして話題を得るプロモーションが増えてきています。
確かに敢えて奇をてらい、バズらせることに繋げることができれば企業の知名度は一気に上がるでしょう。
とはいえ、一般の企業が自分たちだけで「シュール」なデザインを作ることはおすすめできません。
「シュール」な雰囲気は作り込まないと「ウケ狙いをしただけ」のデザインとなるからです。
ウケ狙いの気持ちが見え隠れすれば、学生の心を掴むことは非常に難しくなるでしょう。
「シュール」な雰囲気を作りこむことは「かっこいい」デザインよりも容易ではありません。
よほどの事情がない限りは、「シュール」なデザインは避けましょう。
どうしても「シュール」な雰囲気を目指してスライドデザインやプロモーションを行いたいと考える場合は、プロのデザイナーや制作会社に依頼して作り込んでもらうことをおすすめします。
プレゼンターの研修は必要?
結論からお伝えすると、「ぜひやっていただきたい」です!
研修を行えば当日のプレゼンの質を上げられます。
では、プレゼンの質を上げた際にはどのようなメリットが得られるのでしょうか。
- 企業の魅力が伝わりやすくなり、応募数の増加や母集団の形成が可能になる
- 現場で働いている社員に対して好印象を感じ、企業イメージの向上につながる
具体的な研修については次の記事で紹介しています。ぜひこちらもご覧ください!
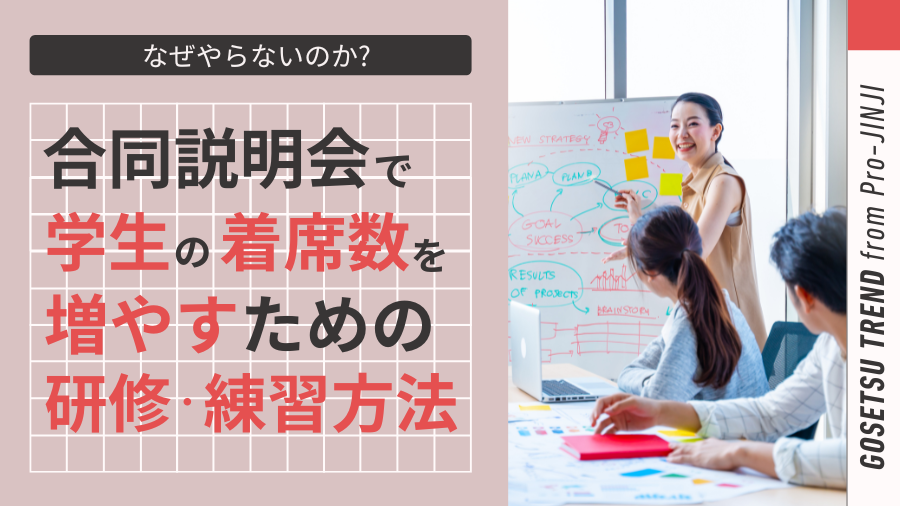
ノベルティ
ノベルティグッズも「採用ブランディング」を目指すのであれば重要な手法です。
ブースに着席した学生に配布すれば、より企業イメージを的確に伝えることができるでしょう。
ノベルティはコーポレートカラーやロゴを基調に、エコバッグやステーショナリーなど実用性が高いものを選びます。
ただし、ノベルティはあくまでも「補助」です。最終的に好印象を与えるのは企業側の姿勢が重要であることを心がけましょう。
ノベルティについては次の記事でも解説しています。ぜひこちらもご覧ください!
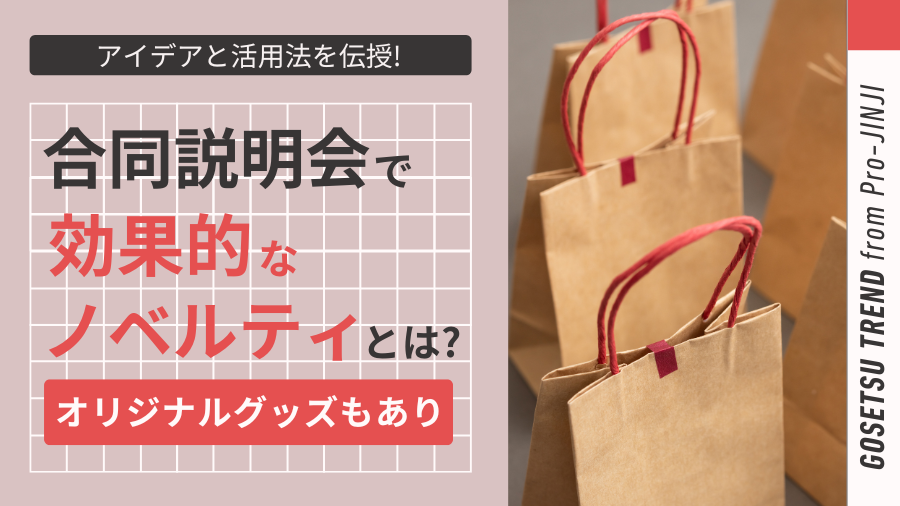
ブランド効果の測定と改善する方法
採用ブランディングを行い、合同説明会を行ったら測定と改善を行います。
手法については以下を参考にしてください。
ブース運営に携わったメンバーが学生の様子を観察します。
また、説明会後に学生のアンケートを行い、率直なフィードバックを得られるよう事前準備しておきます。
「STEP1」のフィードバックをもとに、どの点が関心を惹き話題になったかを検証します。
ポジティブな内容に加えて、改善点や第三者のフィードバックも獲得しておきましょう。
「STEP2」で得られた評価から、改善点を洗い出します。
特に重要な点は「選考に参加する学生のポジティブな声」を参考にしすぎないことです。
選考に参加する学生は忖度をして「動画は参考になった」など前向きに話をしてくれるためです。
アンケートを行った際率直な意見があれば、そちらもきちんと参考にした上で、次回の採用ブランディングに活かしましょう。

合同説明会の運用代行、研修はプロ人事へ!
プロ人事では合同説明会を活用する支援を行っています。
サービスの導入、ご相談はメールフォームからご相談ください!
2営業日以内に担当者よりご連絡させて頂きます。
\ 期間限定・今なら無料の初回コンサルティング付き!/
無料の初回コンサルティングは予告なく終了する場合がございます。
採用ブランディングを通して集客率を上げよう!
いかがだったでしょうか。
採用ブランディングを通して企業のブランドイメージを上げれば、求人への応募を増やすことができるでしょう。
また、合同説明会は当初企業に興味を持っていなかった学生も、関心を惹きつける貴重なチャンスです。
そのためにも企業の魅力を的確にアピールするためにも、採用ブランディングはよりしっかりと行うべきと言えます。

採用ブランディングは
こちらでも詳しく解説中!

プロ人事が運営している採用代行メディア「SaiDai」では、採用ブランディングについてまとめた
記事を取り扱っています。
採用ブランディングについてまとめた情報やノウハウをぜひご覧ください!
※SaiDai内「ブランディング」のカテゴリーページに遷移します。
“合同説明会トレンド” では、この他にも合同説明会の参加に役立つ情報を発信しています。
ぜひ他の記事もご覧いただき、合同説明会の運用に役立てていただけると嬉しいです!