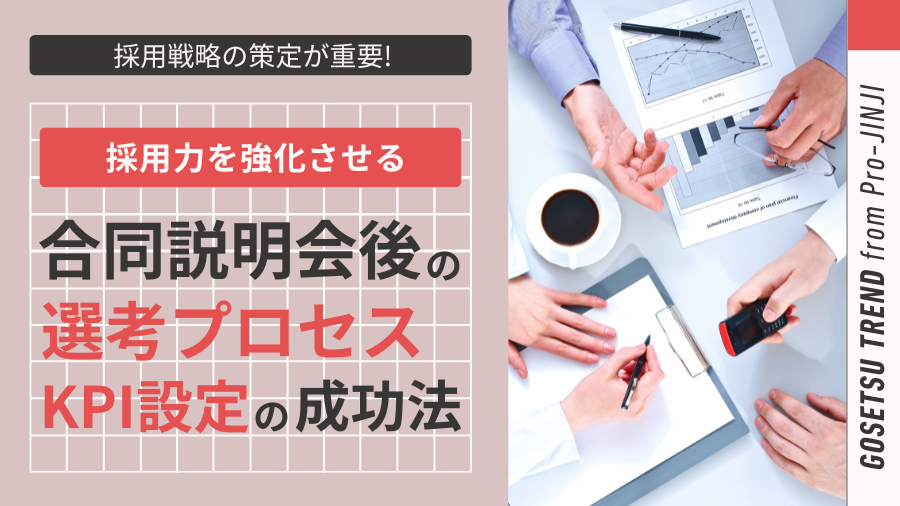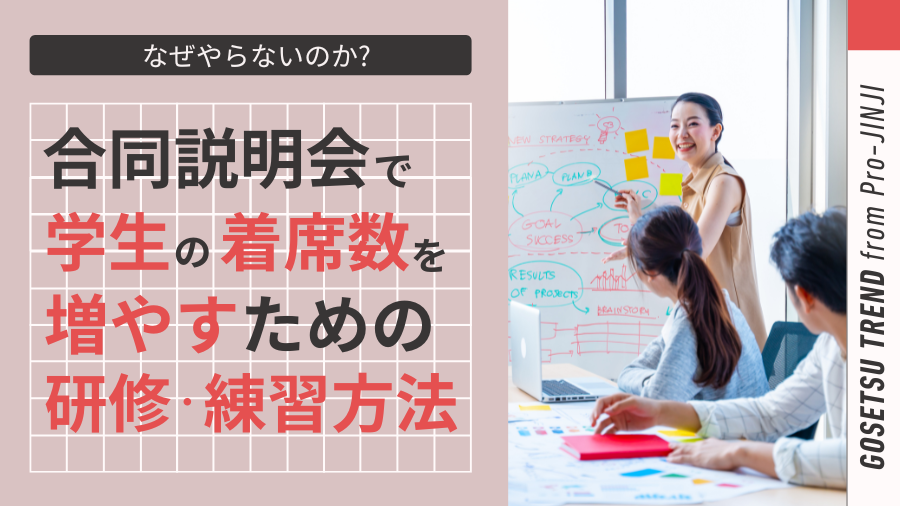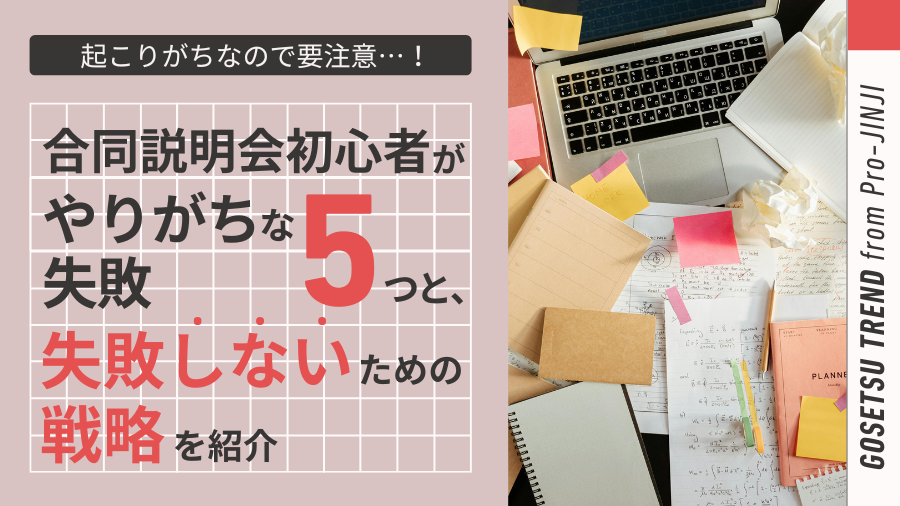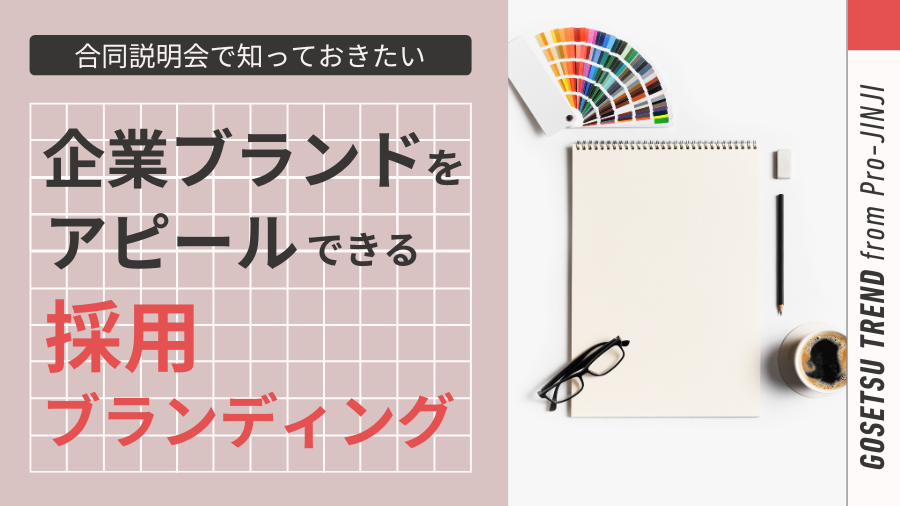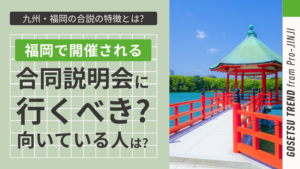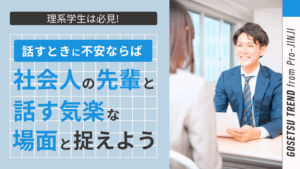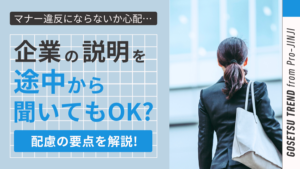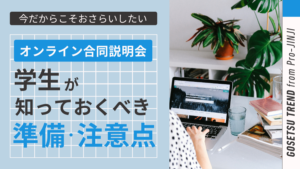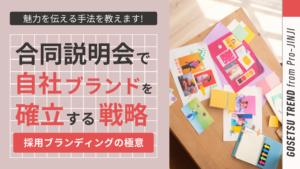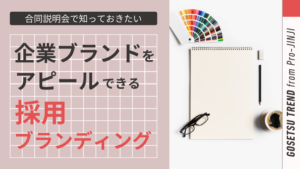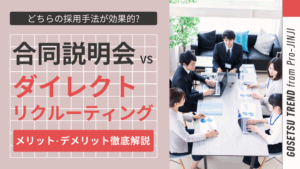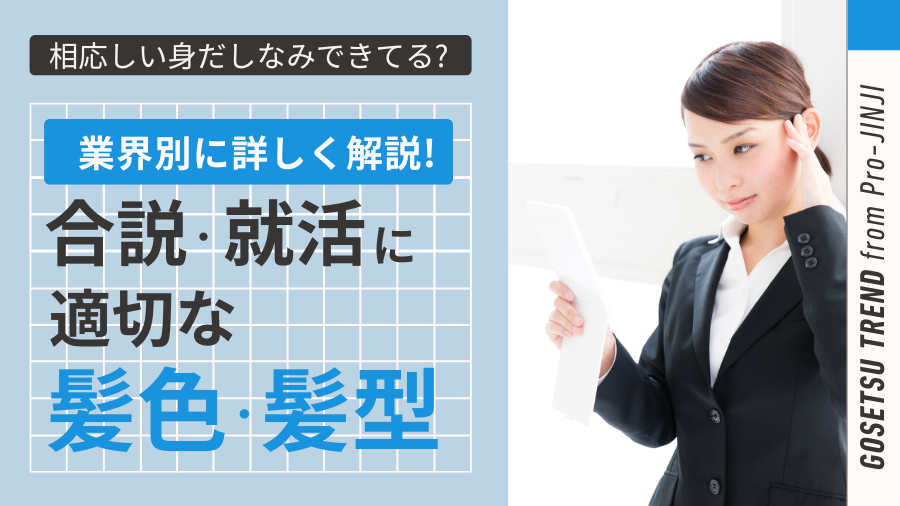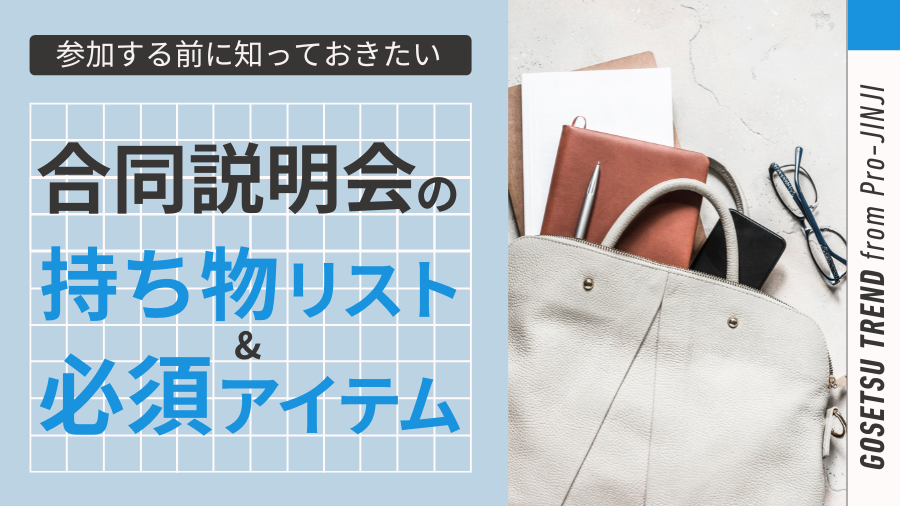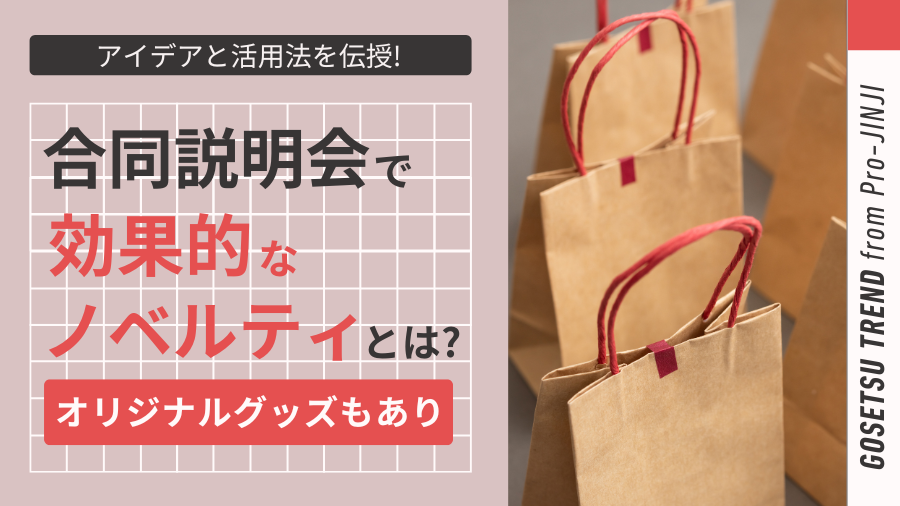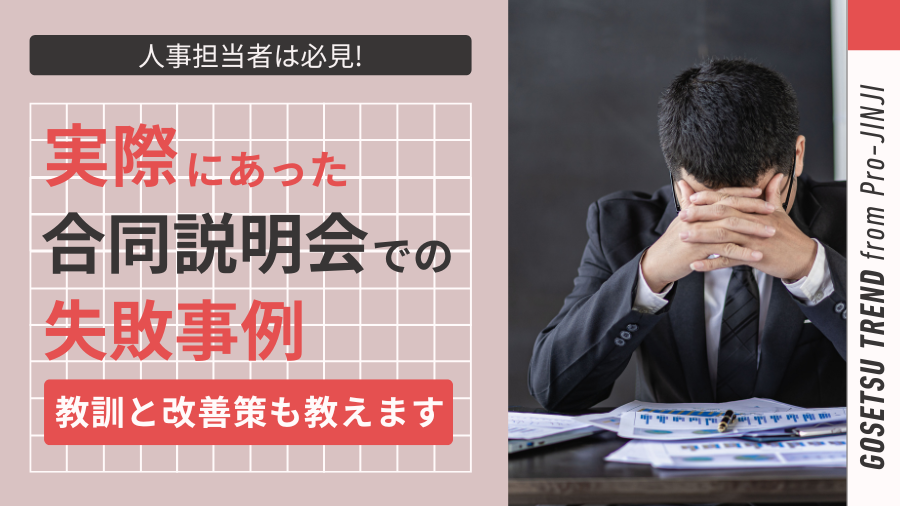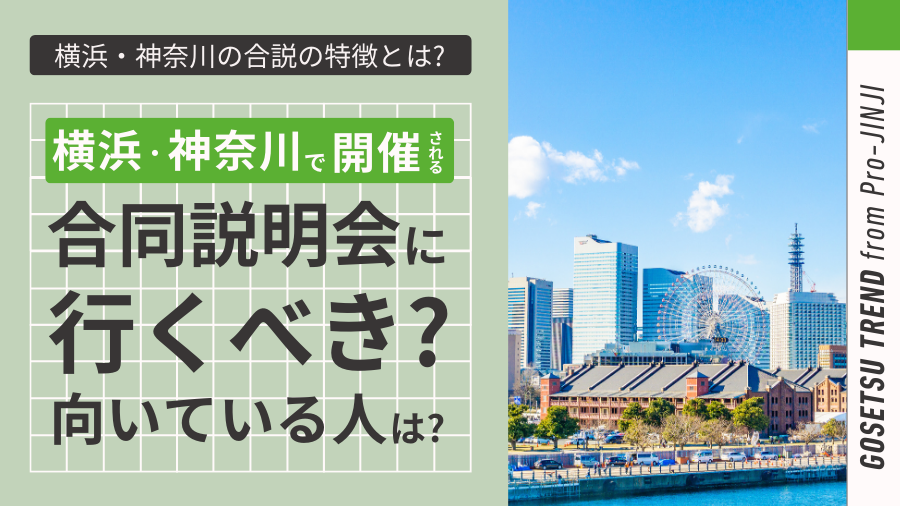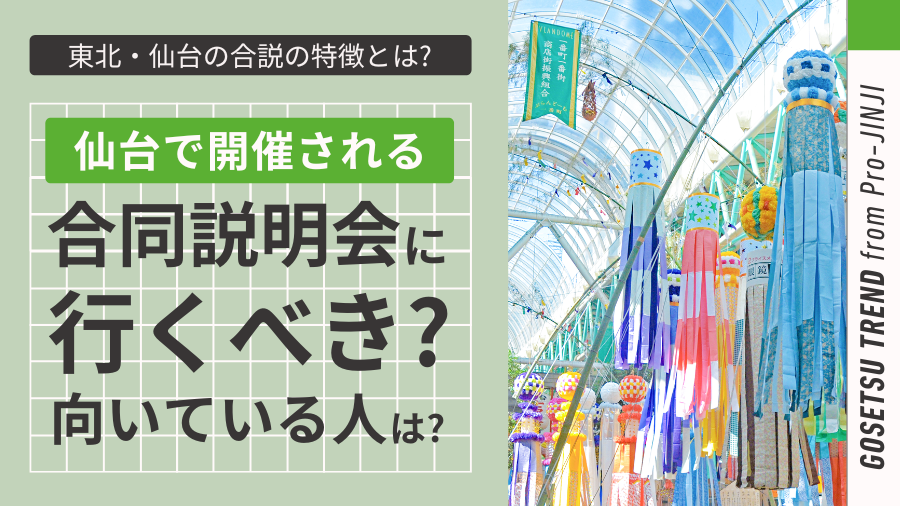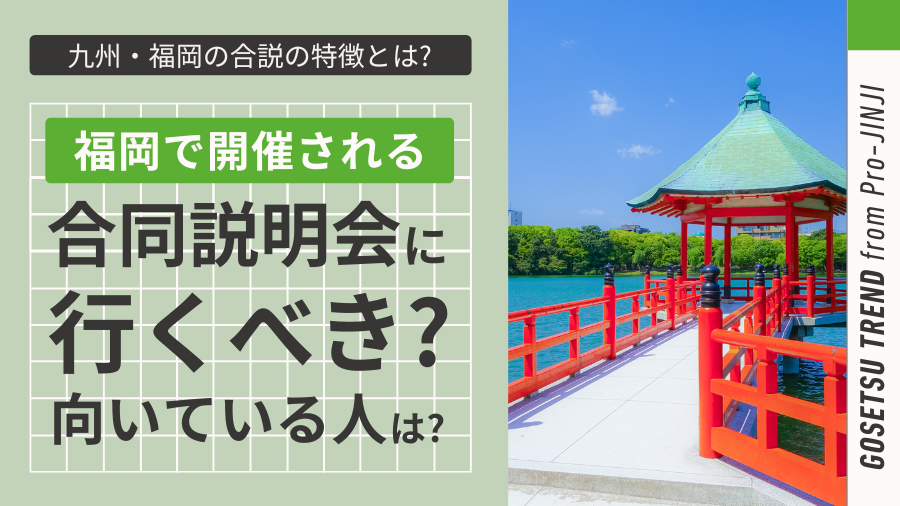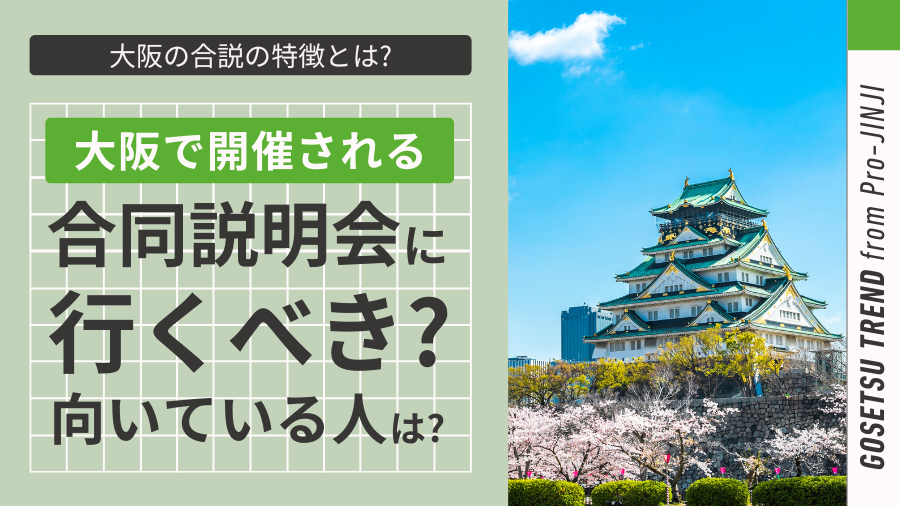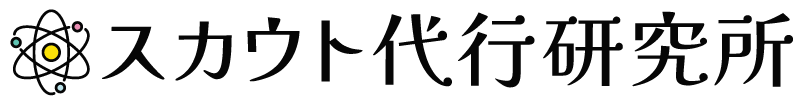こんにちは。プロ人事です。
プロ人事は採用専門のコンサルティング企業であり、合同説明会の運営についてのご相談を承っております。
ブースの運営や採用への進み具合についてご相談に応じていく中で、合同説明会は「ブースの出展さえすれば、あとは自動的に自社に興味を持ってくれる学生がたくさん来てくれて、その流れで選考に参加してくれる」という幻想を抱いてしまっている企業が非常に多いことに気づきました。
言葉にすると「そんなことはない」と考えてしまいます。
しかし、実際には高額な出展料を支払うだけでも高いコストを要しているため、「合同説明会にさえ出れば自社に興味を持ってくれる学生が来る」と考えてしまいがちです。
その結果、企業にとって魅力的な学生は来ないまま、合同説明会の出展は失敗に終わってしまうケースが多くなります。
確かに、採用に困っている企業や課題を感じている企業にとって、合同説明会は非常に有効な手法になります。
では、上記の失敗を防ぐためにはどうすべきか。
それは、合同説明会後の選考プロセス・KPI設定が重要です。
この記事では、学生の採用力をより上げられるための選考プロセス・KPI設定についてプロの人事が詳しく解説していきます!
KPI設定と選考への参加率の上げ方は前回の記事でも解説しています!
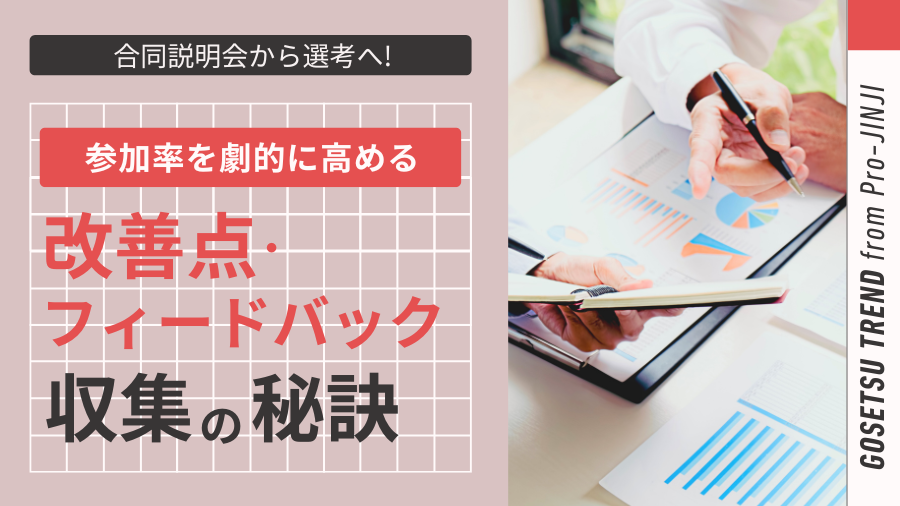

合同説明会の運用にお困りですか?
株式会社プロ人事では、合同説明会の運用代行やご相談に応じています。
プロの人事が展開する採用サポートをご体感ください。
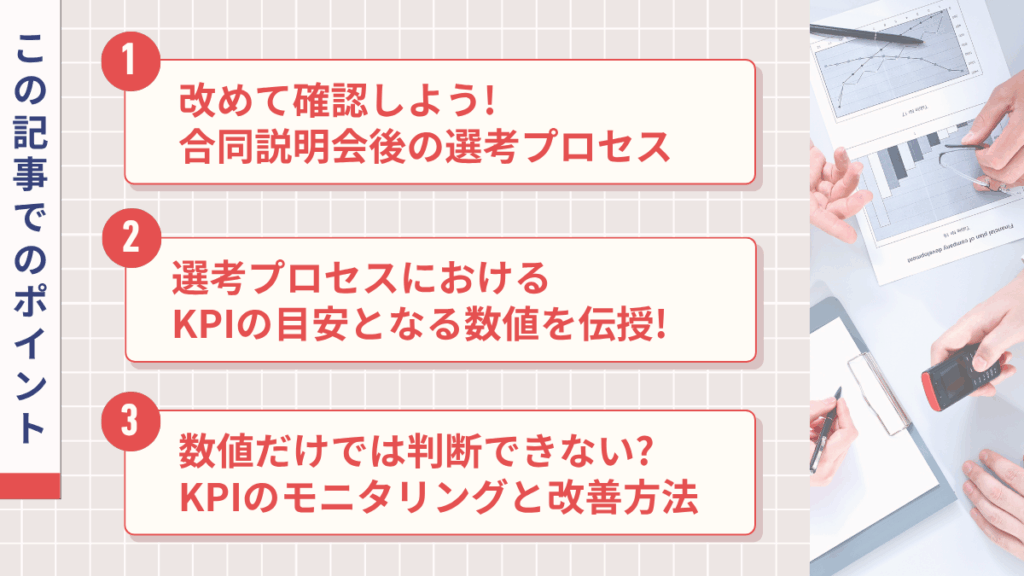
合同説明会後の選考プロセスの設計
まずは採用活動全体を踏まえたうえで、 合同説明会から内定までの流れを改めて確認しましょう。
一般的な合同説明会後の選考プロセスは以下の通りです。
学生が合同説明会 (単独説明会) に参加して、企業の情報や魅力、採用情報を把握します。
合同説明会で興味を持った学生が、企業が単独で開催する会社説明会に参加します。
企業によっては単独説明会で簡易な面談とアンケートをもって、書類選考に替えることもあります。
企業の選考参加を希望する学生から提出された履歴書、エントリーシートから面接に通過する学生を選考します。
一次面接は応募者を絞り込むのが目的です。
そのため人事担当者が面接官となり基本的なビジネスマナーや志望動機、自己PRを通して候補者のコミュニケーション能力を見ていくと良いでしょう。
応募者を絞り込む方法として集団面接やグループディスカッションを導入する手法もあります。
一次面接で候補者を絞り込んだら、二次面接で企業との適合度や個人の人柄、能力をさらに深掘りしていきます。
面接官は現場責任者が担当することが多い傾向です。
一次面接の回答をもとに、入社への意欲や活躍のイメージについて精査していきましょう。
(二次面接を行わず、一次面接通過後にSTEP6の最終面接を行う場合もあります。)
これまでの面接をもとに応募者の適正や能力、入社への熱意を企業との社風に適合するか最終的に見極めます。
企業にとっては採用の判断が最終面談で決まるため、役員が面接官として参加することが多い傾向です。
応募者の入社意欲やキャリアビジョン、企業への深い理解度が見極めるポイントとなるでしょう。
採用が決まったら、学生に内定を通知します。
学生が内定を承諾したら正式に採用です。
選考フローにおいては各社によって内容は異なるため、上記で挙げているフローとは異なることも多いでしょう。
しかし、細かな点は異なったとしても、大まかな内容などは変わりません。
前提として「学生が応募して、選考して、内定を提示して、内定承諾を受ける」ことはどのような会社であれ、変わらないはずです。
また、選考では単独説明会当日の書類選考や、一次面接でのグループディスカッション、グループワークを導入することもあります。
選考プロセスが多いと企業と適合する学生を選べる可能性が高まりますが、学生が応募をためらう事例も出てくるでしょう。
選考プロセスを増やしすぎると人事・企業の採用業務が増加する懸念もあります。
逆に選考プロセスが少なすぎると内定が早く欲しい学生が集まり、応募が増加する傾向にありますが、限られた選考での情報で学生の適正や人柄・スキルを見極めなくてはなりません。
その分企業と学生のミスマッチを誘引するリスクが増えると言えるでしょう。
企業が求める人材や学生の応募数、企業・人事の業務リソースを都度鑑みながら、選考プロセスを構築していくことをお勧めします!
選考プロセスにおけるKPIの目安となる数値
次に、選考プロセスにおいて目安となるKPIについて、それぞれの数値を見ていきましょう。
今回は「合同説明会から選考への予約率」と「内定承諾率」の2点に着目してご説明します!
KPIとは、Key Performance Indicator(重要経営指標)のことです。
業績の評価や事業の最終目標達成のために必要なプロセスがどれくらい進んでいるか、中間目標としての達成度を図るために設定されています。
人材採用におけるKPIというのは、以下のように定義づけされることが一般的です。
応募(エントリー)→書類選考→一次面接→最終面接→内定→内定承諾
人事のKPIゴール (KGI:Key Goal Indicator)は「内定承諾」です。※応募者のゴールは「内定」で止まる
① 合同説明会から選考への予約率
25%〜50%
合同説明会のブースで説明を聞いてくれた学生の中から、選考への参加を予約した割合のデータです。
数値が低い場合
選考の予約率についての数値が低い場合は企業の魅力をブースで伝えきれていない可能性があります。
特に低い場合の改善方法としては「プレゼンの練習」が重要です。
以下の記事からプレゼンの練習・企業でできる合同説明会の運用・研修の方法についてもご覧いただけますので、ぜひ併せてご覧ください!
プレゼンの練習・企業での研修方法はこちらからご覧ください!


合同説明会の運用代行、研修はプロ人事へ!
プロ人事では合同説明会を活用する支援を行っています。
サービスの導入、ご相談はメールフォームからご相談ください!
2営業日以内に担当者よりご連絡させて頂きます。
\ 期間限定・今なら無料の初回コンサルティング付き!/
無料の初回コンサルティングは予告なく終了する場合がございます。
また、先述の「合同説明会からの採用プロセス」が多すぎる、選考項目が煩雑すぎる場合も学生が応募にためらい、選考への予約を見送る可能性があるでしょう。
数値が低すぎる場合は採用プロセスで不必要な手法があるかを見直してみることをお勧めします。
数値が高い場合
この数値は「高いほど選考に進みたい・学生が自社に魅力を感じてくれている」という理由から、高ければ高いほど良いと思われるかもしれません。
実は、数値が高いから結果が良好と言えるかというと、そうとは限らないのが現状です。
この数値が高すぎる場合には、「もともと自社に興味がある学生しか話を聞いていなかった」可能性もあるからです。
せっかく、合同説明会に出展しているのであれば「当初は興味がなかった学生」にも話を聞いてもらうように取り組むべきです。
合同説明会では会場に一度に多くの企業が集まる特性を持つことから、自社に対して興味がない・今まで存在を知らなかった学生にも企業の魅力をアピールするチャンスです。
集客の方法について検討・改善を勧めることをおすすめします。
ブース運営のおすすめ記事はこちらもご覧ください!
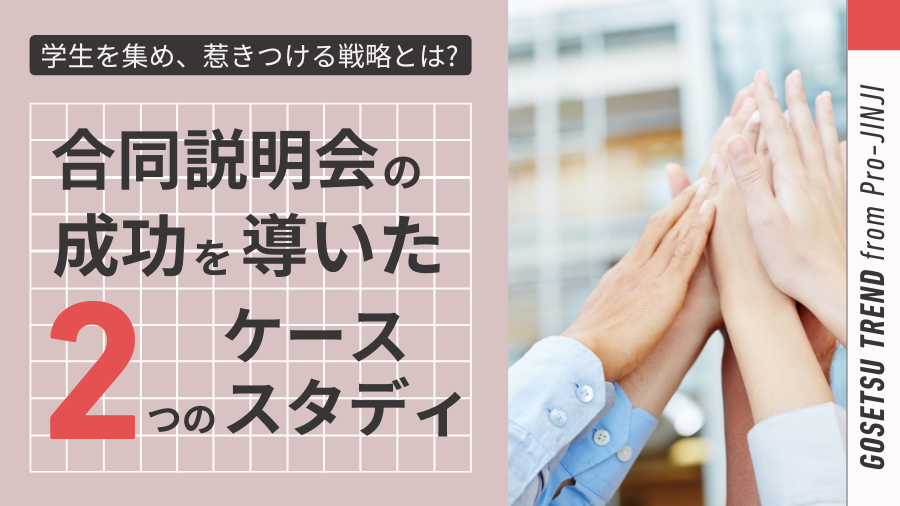
採用プロセスにおいては「一次面接確約・書類選考なし」「面接1回だけで採用」など、「内定をすぐに出してくれそう」と捉えられやすい手法だと選考への予約率も高まる傾向にあります。
内定承諾率
20%〜40%
内定を出した学生に対して、承諾した割合のデータです。
数値が低い場合
この数値については低すぎる場合には、様々な理由が考えられます。
内定承諾率の数値が低い原因
- 自社の魅力の訴求が学生に対して不十分である
- 学生が内定に対して積極的でないか、納得感がない
- 魅力や待遇が競合他社に負けている
特に、内定承諾率が20%を下回るとと危険水域といえます。
上記の数値の低さの理由をもとに、早急に対策を考えていきましょう。
数値が高い場合
一方で内定承諾率が高すぎるのも問題です。
その理由は、「実は内定承諾率は簡単かつ人為的に数値を高めることが可能だから」です。
具体的な手法として、「内定を承諾しそうな雰囲気の学生」「選考で内定を承諾することを約束した学生」だけに特化して内定を出します。
すると内定を辞退する学生は必然的に排除されるため、それに伴い内定承諾率を高めることができます。
近年では「内定承諾率を高めるコンサルティング」などを標榜する企業やサービスもあるほどです。
「内定承諾率が高いから良い」と一概に判断するだけでなく、上記の可能性を踏まえながら慎重にKPIを測定するようにしましょう。
KPIのモニタリングと改善方法
KPIの改善については、数値だけでなく「KPIの中身」にまで目を向けて改善をしていくことをオススメします。
内定承諾率を低くさせる戦略もある?
KPIの数値の分析でよく挙げられる「内定承諾率」についても実態を踏まえて戦略的に決める必要があります。
その中で意図的に内定承諾率を低くさせる戦略があることをご存知でしょうか?
実際にある企業では「内定承諾率」を高くせず、敢えて下げようと取り組んでいる事例もありました。
この事例はかなり特殊なケースであり、戦略的に行わないと非常に高いリスクに変わってしまいます。
全ての企業にもオススメできる手法ではないので、あくまで「数値を人為的に変動させる手法の1つ」として捉えていただきますようお願いいたします。
実際に取り組まれていた内定承諾率を下げるプロセス
合格者に内定を提示するまでは通常通りの選考を行います。
内定提示後に学生に対して個別面談等の場を設け、本音で話す機会を設けます。
面談では学生が心から望む本音や希望について話し合い、その上で「自社の考えが合っていないと考えるのであれば、内定を辞退してほしい」と迫ります。
なぜこのような取り組みが行われるのか?
「内定がほしいためにが学生本音を隠す・ずらす・偽る」というのが多かれ少なかれ発生し、
企業側にとっては「“内定が出るまでは”学生が本音で話してもらえない」と考えているためです。
これが結局のところ「入社後の活躍へのミスマッチ」であったり、「退職」に至るリスクにつながります。
そのため先に「内定」を伝え、学生が安心したところで本音で話す場をすることで、改めて「企業と学生のマッチ度」をよりクリアに確認する場を作ることができます。
本音で向き合った結果適合しないと判断した学生が内定を辞退するため、上記の手法を敢えて導入することで内定承諾率を下げているケースもあります。
数値だけでは判断できない
前述の通り数値は人為的に操作が可能であり、また操作をせずとも他の要因で数値が変動する可能性が高いためです
そのため、KPIは表面的な数値だけでなく、「なぜその数値になったか」について、背景や要因を分析する必要があるといえるでしょう。
単に「数値が高いか低いか」だけで判断してはいけません。
また、KPIの数値だけを改善しようと動くと、採用プロセスや手法に影響がでてしまう可能性もあります。
数値の背景や要因に着目し、改善できるところのみ対策していくようにしましょう。
KPIは数値だけでなく「要因や背景」にも着目しよう。
いかがだったでしょうか。
つい結果の数値に一喜一憂してしまいますが、大切なのは「なぜその結果になったのか、要因や背景に着目して分析すること」です。
数値が低くても適切な手法であれば成功とも言えますし、逆に高い背景に改善点があれば対策する必要があると判断できます。
とはいえ、数値や背景がどこまで適切で、どこから改善・対策すべきか。
手法を含めて時にお悩みになる時があると思います。
その際は私たち「プロ人事」がお力になれますので、些細な疑問でもぜひお聞かせいただけると嬉しいです!
“合同説明会トレンド” では、この他にも合同説明会の参加に役立つ情報を発信しています。
ぜひ他の記事もご覧いただき、合同説明会の運用に役立てていただけると嬉しいです!